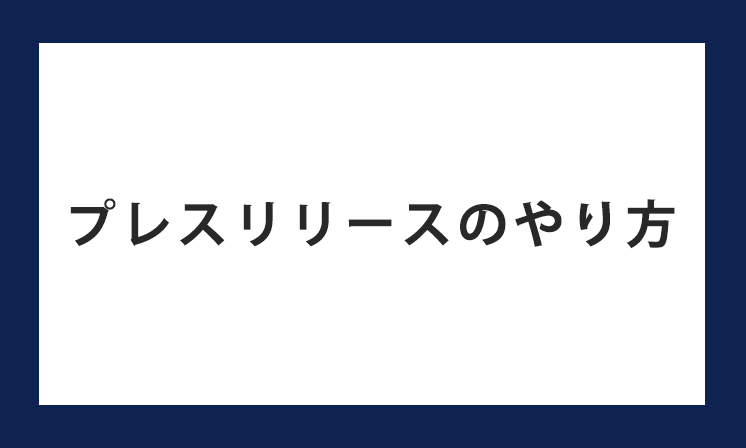
自社の新商品や新サービスを広く知ってもらう手段として、多くの企業・団体が活用しているのがプレスリリースです。
しかし、「配信の流れがよく分からない」「注意すべき点はある?」と悩む方も少なくありません。
プレスリリースは、正確かつ効果的に作成・配信することで、メディアに取り上げられる可能性が高まり、PR効果を大きく向上させられます。
そこで今回の記事では、プレスリリースの基本的なやり方や配信方法、作成・配信の流れ、注意すべきポイントなどを詳しく解説します。
- プレスリリースの作成から配信までの基本的なやり方・流れ
- ・その1 プレスリリースを配信する目的・ターゲットを定める
- ・その2 プレリリースの配信内容を決める
- ・その3 配信日時を決める
- ・その4 プレスリリース原稿を作成する
- ・その5 わかりやすい画像・写真・グラフを用意・挿入する
- ・その6 配信先を選定し、メディアリストを作る
- ・その7 送付方法を決める
- ・その8 最終チェックを行う
- ・その9 プレスリリースを配信する
- プレスリリースの配信先・送付先は?
- ・プレスリリース配信サービスを利用する
- ・記者クラブに投稿する
- ・メディアに直接送付する
- プレスリリース配信完了後にすること
- ・分析結果をもとに効果測定する
- ・内容に間違いがあった場合は訂正配信をする
- ・記事が掲載された際は、自社ホームページやSNS等で発信する
- プレスリリース作成時の注意点
- ・客観的な根拠のない最上級表現をしていないか
- ・専門用語・難しい言葉は極力使っていないか
- ・記載内容に間違いがないか
- まとめ
プレスリリースの作成から配信までの基本的なやり方・流れ

プレスリリースの効果を最大限に引き出すには、単に原稿を作成して配信するだけでは不十分です。
目的やターゲットの設定、配信内容の整理、メディアの選定、そして最終チェックまで、各工程を正しく理解し、丁寧に進めることで成果につながります。
ここでは、プレスリリースの作成から配信までの基本的なやり方と流れを詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
その1 プレスリリースを配信する目的・ターゲットを定める
プレスリリースを作成する際は、まず「誰に」「何を」伝えたいのかを明確にすることが重要です。
新商品の発表や業界メディアへのPRなど、目的によって内容や配信先は大きく異なります。
そのため、まずは配信目的やターゲットをしっかりと定めましょう。
その上で、ターゲット層や配信先メディアの特性を意識することで、より効果的な情報発信が可能です。
このように、目的とターゲットの設定は、全ての工程の土台となる重要なステップになります。
その2 プレリリースの配信内容を決める
プレスリリースの目的やターゲットが明確になったら、次は伝えたい情報を整理し、世の中にとって価値のある内容に仕上げることが重要です。
単に自社の伝えたいことを並べるのではなく、社会性・ニュース性・話題性といった視点を取り入れることで、メディアに取り上げられる可能性が高まります。
また、主な内容に加えて、補足情報や数値データなどを効果的に盛り込むことも重要です。
こうした構成を意識することで、情報の説得力と信頼性が高まります。
その3.配信日時を決める
プレスリリースの効果を最大限に発揮するためには、配信日時も戦略的に考えることが重要です。
一般的には、週明けすぐや週末・祝日前後は避け、火曜〜木曜の10時〜15時頃が理想とされています。
この時間帯は、メディア関係者が情報収集をしやすいとされているためです。
また、競合他社の発表や大きな時事ニュースと重ならないように配慮することで、プレスリリースが他の情報に埋もれにくくなります。
その4 プレスリリース原稿を作成する
配信内容や日時などが定まったら、いよいよプレスリリースの原稿を作成します。
その際は、読み手にとってわかりやすく必要な情報が、過不足なく伝わる構成にすることが重要です。
基本構成には、「タイトル」「リード文」「本文」「会社情報(問い合わせ先)」の4要素が含まれます。
中でもタイトルとリード文は、メディア関係者や読者の目に最初に触れる重要な部分のため、簡潔かつ魅力的に仕上げましょう。
タイトルには、目を引くトレンド感やニュース性のあるキーワードを盛り込むと効果的です。
また、リード文には「誰が」「何を」「いつ」「どこで」「なぜ」「どのように」といった5W1Hの要素を取り入れることで、正確かつ具体的な情報が伝わりやすくなります。
プレスリリースの書き方に関しては、以下記事で詳しく解説しています。
https://www.doublequotationmarks.com/29/
https://www.doublequotationmarks.com/46/
その5 わかりやすい画像・写真・グラフを用意・挿入する
視覚的な情報は、内容の理解を助けるだけでなく、読者の関心を高めるための重要な要素です。
文章だけでは伝わりにくい情報を補うために、画像や写真、グラフなどを適切に挿入しましょう。
その際は、画質の良い写真を使い、わかりやすいキャプションを添えることも大切です。
また、メディア関係者がそのまま使用できる素材を用意しておくことで、掲載される可能性を高めることもできます。
その6 配信先を選定し、メディアリストを作る
原稿が完成したら、次は配信先を選定し、メディアリストを作成します。
プレスリリースの内容に合ったメディアを選定することは、情報を広く正しく届ける上で非常に重要です。
業界紙や専門誌、Webメディアなど、ターゲットに合った媒体をリストアップしましょう。
その際は、記者名や担当部署なども事前に調べておくと、より適切な相手に届きやすくなります。
その7 送付方法を決める
プレスリリースは、メール、FAX、郵送、直接訪問など、さまざまな方法で送付できます。
中でもメールは最も一般的で、迅速かつ手軽に多くのメディアへ配信できることが特徴です。
また、FAXは業界紙や地方新聞社などで現代も活用されることがあり、郵送は公式性を重視したい場合や丁寧な印象を与えたい場合に効果があります。
関係性が構築できているメディアに対しては、直接訪問という方法も有効です。
いずれの方法でも、相手の立場に配慮した丁寧な文章を心がけ、誤送信や重複送信の防止にも十分注意しましょう。
その8 最終チェックを行う
原稿が完成したら、配信の前に必ず最終チェックを行いましょう。
誤字脱字はもちろん、情報の正確性やリンクの動作確認、表現の分かりやすさなどを丁寧に確認します。
また、一人の目だけではなく、複数人でチェックを行うことで、見落としに気づける可能性が高まります。
ミスのあるプレスリリースは、企業やサービスへの信頼を損ねる恐れがあるため、念入りな確認作業を心がけましょう。
その9 プレスリリースを配信する
全ての準備が整ったら、いよいよプレスリリースを配信します。
配信後はメディアや一般消費者からの問い合わせに備え、迅速な対応ができる体制を整えておきましょう。
また、掲載された記事の確認や社内での共有も忘れずに行い、今後の広報活動の改善につなげていくことが大切です。
プレスリリースの配信先・送付先は?

プレスリリースを作成したら、次に重要なのは「どこに届けるか」です。
ここでは、代表的な配信手段であるプレスリリース配信サービスの活用、記者クラブへの投稿、そしてメディアへの直接送付について、それぞれの特徴や活用方法を詳しく解説します。
プレスリリース配信サービスを利用する
プレスリリース配信サービスは、多数のメディアに一斉配信できる便利な手段として、多くの企業や団体に利用されています。
業種やエリア別に配信先を選べるサービスも多く、メディア掲載の可能性を広げられる点が大きな魅力です。
また、事前に作成した原稿を登録するだけで配信が完了するため、広報に不慣れな方でも手軽に始められるのもメリットだと言えるでしょう。
代表的なサービスには「PR TIMES(ピーアールタイムス)」や「@Press(アットプレス)」などがあり、目的や予算に応じて選ぶと効果的です。
プレスリリースの配信サービス、費用に関しては、以下記事で詳しく解説しています。
https://www.doublequotationmarks.com/94/
記者クラブに投稿する
記者クラブにプレスリリースを投稿することで、新聞・テレビ・通信社などの報道機関に情報を届けることができます。
記者クラブ経由の情報は、信頼性の高い内容として扱われやすく、報道のきっかけとなるケースも少なくありません。
ただし、投稿のルールや受付条件はクラブごとに異なるため、事前の確認が必要です。
また、紙媒体での提出が求められることもあるため、スケジュールには十分な余裕をもって準備しましょう。
プレスリリースの「記者クラブ」への投げ込みに関しては、以下記事で詳しく解説しています。
https://www.doublequotationmarks.com/84/
メディアに直接送付する
掲載を希望するメディアが明確な場合には、記者や編集部にプレスリリースを直接送付する方法も効果的です。
その際は、送付先の部署や担当者を事前に特定しておくことで、確実に情報が届けられやすくなります。
特に日頃から関係性を築けているメディアであれば、掲載の可能性がさらに高まるでしょう。
プレスリリース配信完了後にすること

プレスリリースは配信したら終わりではなく、配信後の対応も広報活動において非常に重要です。
ここでは、プレスリリース配信完了後に行うべき主な対応について詳しく解説します。
分析結果をもとに効果測定する
プレスリリースの成果を把握するためには、配信後の効果測定が欠かせません。
掲載されたメディアの数、記事のPV数、SNSでの拡散状況、Webサイトへの流入数などを指標に、配信内容やタイミングが適切だったかを振り返りましょう。
これらのデータをもとに客観的に分析することで、次回の改善点が明確になり、より効果的な広報戦略へとつなげることができます。
プレスリリースの効果測定に関しては、以下記事で詳しく解説しています。
https://www.doublequotationmarks.com/363/
内容に間違いがあった場合は訂正配信をする
プレスリリースの内容に誤りがあった場合は、できるだけ早く訂正情報を配信しましょう。
情報の正確性は企業の信頼に直結するため、迅速かつ誠実な対応が求められます。
訂正の際には、誤っていた箇所と正しい内容を明確に示し、必要に応じて謝罪文を添えるのが一般的です。また、配信先のメディアには個別に連絡し、掲載内容の訂正や差し替えを依頼しましょう。
さらに、SNSなど拡散力の高い媒体で誤情報が広まった場合は、自社のホームページでも訂正情報を発信し、適切に対応することが大切です。
記事が掲載された際は、自社ホームページやSNS等で発信する
プレスリリースを通じて自社の情報がメディアに掲載された場合は、その情報を自社のホームページやSNSなどで積極的に紹介しましょう。
掲載記事を二次活用することで、広報活動の成果を社外にも社内にも効果的に伝えることができます。
特に信頼性の高いメディアに取り上げられた場合は、自社のブランディングや信頼の向上にもつながるため、有効なPR資産として活用しましょう。
プレスリリース作成時の注意点

プレスリリースは、内容の信頼性や読みやすさが非常に重要です。
誤解を招く表現や専門性が高すぎる言葉の使用を避け、情報の正確性にも十分に配慮しなければ、メディアに取り上げられにくくなるだけではなく、企業イメージを損なう可能性もあるため注意しましょう。
ここでは、プレスリリース作成時の注意点を解説しますので、ぜひ参考にしてください。
客観的な根拠のない最上級表現をしていないか
プレスリリースを作成する際、自社の商品やサービスを魅力的にアピールしたいと考える広報担当者は多いでしょう。
しかし、「業界No.1」「最高品質」「最高峰サービス」といった最上級の表現は、根拠がなければ誤解や不信感を招く恐れがあります。
プレスリリースは、客観的な事実に基づいて情報を伝える文書です。
主観的な表現は控え、第三者のデータや実績など、信頼性の高い情報に基づいた内容を心がけましょう。
誇張や曖昧な表現が含まれると、メディアに掲載されない可能性もあるため、十分に注意が必要です。
専門用語・難しい言葉は極力使っていないか
自社や業界内では当たり前に使われている言葉でも、業界外の人には理解しづらいことがあります。
プレスリリースは広く一般に向けて情報を伝える手段であるため、専門用語や業界用語、略語は必要最低限にとどめ、誰にでもわかりやすい表現に言い換える工夫が大切です。
どうしても言い換えが難しい用語がある場合は、説明を添えるなどして、常に読者が理解しやすいように配慮することを心がけましょう。
記載内容に間違いがないか
プレスリリースを配信する際は、事実関係や数値、固有名詞に誤りがないかを必ず複数回チェックしましょう。
誤った情報を配信すると、企業の信頼を損なうだけでなく、その後の訂正対応が必要になり、関係者に余計な手間をかけてしまう恐れがあります。
そのため、可能な限り複数人で原稿を確認し、誤字脱字や情報の整合性を客観的にチェックできる体制を整えることが理想的です。
まとめ

今回の記事では、プレスリリースの基本的なやり方や配信方法、作成・配信の流れ、注意すべきポイントなどを幅広く解説しました。
プレスリリースを配信する際は、目的やターゲットを明確にし、内容をわかりやすく整理した上で、適切な配信先と方法を選びましょう。
また、誤字脱字や情報の正確性を複数回チェックして信頼性の高い内容に仕上げることや、配信後に効果測定や訂正対応を行い、掲載情報を自社のPR活動に活かすことも重要です。
これらのポイントを押さえれば、プレスリリースを通じて多くのメディア掲載や認知拡大が期待できます。ぜひこの記事を参考に、効果的なプレスリリースの作成に取り組んでみてください。





