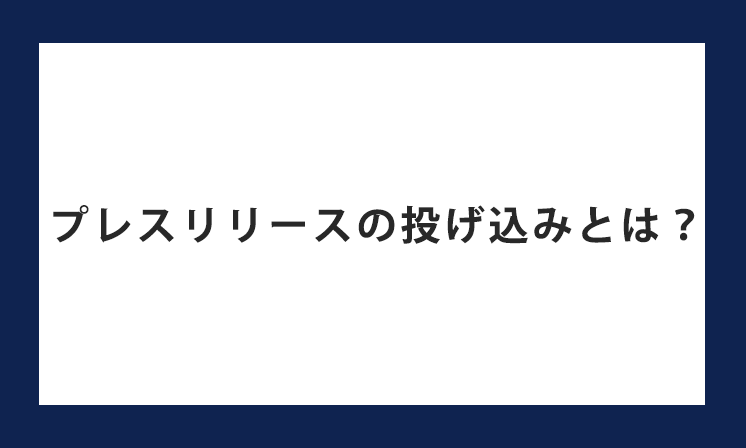
プレスリリースを配信する手段としては、WEB配信やメールが主流となっています。
しかし現在でも、「投げ込み」と呼ばれるアナログな方法でプレスリリースの発信をしている企業や団体も少なくありません。
とはいえ、広報活動を始めたばかりの方にとって、「投げ込み」という言葉自体にあまり馴染みがない場合も多いでしょう。
そこで今回の記事では、プレスリリースの投げ込みについて詳しく解説します。
実際の配信方法や注意点などもご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
- プレスリリースの投げ込みとは?
- プレスリリースの投げ込み先の「記者クラブ」とは?
- ・主な記者クラブの種類
- ・地方の記者クラブと東京や大阪など都会の記者クラブとの違い
- プレスリリース投げ込みのメリット
- ・多くのメディアに一度に情報を届けられる
- ・記者と接点が作りやすくなる
- ・低コストでできる
- プレスリリースの投げ込みのやり方
- 1.投げ込みに適したプレスリリースの内容を決める
- 2.プレスリリースの投げ込み先を探す
- 3.投げ込む記者クラブに連絡をする
- 4.投げ込み方法と必要な部数を確認する
- 5.プレスリリースを記者クラブに持参する
- プレスリリースの投げ込みをするときの注意点
- ・適切な時間・タイミングで投げ込みをする
- ・記者クラブのルールを事前に確認する
- ・宣伝や広告目的の持ち込みはしない
- ・情報量と発信するタイミングは揃える
- ・プレスリリースの内容に沿った記者クラブを選ぶ
- ・同時に別のアプローチも行う
- まとめ
プレスリリースの投げ込みとは?

プレスリリースの投げ込みとは、報道機関(記者クラブ・テレビ局・新聞社など)に対して、自社のプレスリリースを直接届けることを言います。
メールやWEB配信などのデジタル手段ではなく、紙媒体を手で届けるアナログな方法で、飛び込み営業のようなイメージを持つとわかりやすいかもしれません。
投げ込みは、デジタル化が進んだ現在ではあまり見られなくなりましたが、一部の企業や団体では今もこの方法を採用することがあります。
プレスリリースの投げ込み先の「記者クラブ」とは?

プレスリリースの投げ込み先の一つに、「記者クラブ」という団体があります。
この記者クラブとは、テレビ局や新聞社などの報道機関が、特定のテーマ(経済・政治・文化など)に関する取材拠点として設置している組織です。
主に、取材の効率化や情報の公平な共有を目的とし、各報道機関から派遣された記者などで構成されています。
主な記者クラブの種類
ここでは、主な記者クラブの種類を解説します。
■経済産業記者クラブ
経済産業記者クラブは、経済産業省の庁舎内に設置されている記者クラブで、経済・産業・貿易・中小企業政策などに関する情報を専門的に取材しています。
所属しているのは、主にテレビ局や新聞社、通信社の記者が多いです。
経済産業記者クラブには、主に以下のような経済に関する情報が集まります。
- 美容機器の新技術や特許取得、新型スマート家電の発表といった新製品情報
- キャッシュレス決済の普及率などの業界動向
- 省エネ設備導入企業への補助金制度などのエネルギー政策
■文化記者クラブ
文化記者クラブは、文化庁などの関連機関に設置されており、文化・芸術・メディアなどに関する情報を専門に取材しています。
所属しているのは、前項で触れた経済産業記者クラブ同様、主にテレビ局、新聞社、通信社の記者が中心です。
文化記者クラブには、主に以下のような文化に関する情報が集まります。
- 映画、音楽、舞台などのエンターテイメント業界の動向や最新情報
- クリエイターによる展示会や最新のイベント情報
- 教育政策や学校改革、学習支援活動などの教育分野の動向
■スポーツ記者クラブ
スポーツ記者クラブは、スポーツ団体の本部や関連施設、報道機関のオフィス内などに設置されており、プロスポーツ、アマチュアスポーツ、オリンピックなどに関する情報を専門的に取材しています。
所属しているのは、テレビ局、新聞社、通信社、スポーツ専門誌の記者が多いです。
スポーツ記者クラブには、主に以下のようなスポーツに関する情報が集まります。
- スポーツ業界のトレンドやチーム運営に関する最新ニュース
- 各スポーツの試合結果や選手のパフォーマンスなどの速報
- 競技に関連する新ルールや改革に関する最新情報
■環境記者クラブ
環境記者クラブは、政府機関や環境関連団体などに設置されており、環境問題や自然保護、気候変動などに関する情報を専門的に取材しています。
所属している記者は、テレビ局、新聞社、通信社が中心ですが、環境に特化したメディアの記者も参加していることが多いです。
環境記者クラブには、主に以下のような環境問題に関する情報が集まります。
- 政府や地方自治体が発表する新しい環境政策、温暖化対策に関する方針
- エコカー、省エネルギー技術、廃棄物リサイクルに関する新技術の発表
- 太陽光、風力、バイオマスなどの再生可能エネルギー技術に関する新しい取り組みの発表
■交通記者クラブ
交通記者クラブは、国土交通省などの官庁内に設置されていることが多く、交通や運輸、インフラに関する情報を専門的に取材しています。
所属しているのは、テレビ局、新聞社、通信社、交通インフラ業界に特化したメディアの記者などです。
交通記者クラブには、主に以下のような交通インフラや生活に密着した情報が集まります。
- 鉄道会社の経営情報や業績発表、新路線の開通に関する情報
- 航空会社の新路線や運航スケジュールの変更に関する情報
- 国土交通省や地方自治体による交通政策の発表
■兜倶楽部(かぶとくらぶ)
兜倶楽部は、東京・兜町にある東京証券取引所内に設置されており、証券、金融、経済分野を専門的に取材する記者クラブです。
経済報道の中枢ともいえる兜倶楽部は、株価や企業経営に影響を与える情報をリアルタイムで発信する、非常に重要な拠点とされています。
そのため、所属する記者は、テレビ局、全国紙の経済部・金融担当記者、経済誌・ビジネス誌の記者など、証券・金融に関する高度な専門知識を持つ人材が中心です。
兜倶楽部には、主に以下のような証券市場や経済全般に関する情報が集まります。
- 東証の株価変動や日経平均の推移といったリアルタイム情報
- M&A(企業の合併・買収)、新規上場(IPO)、社長交代などの経営に関する重要情報
- GDP(国内総生産)成長率、失業率、物価指数などのマクロ経済に関する統計データ
■東商記者クラブ
東商記者クラブは、東京商工会議所(東商)内に設置されており、主に中小企業・商工業・地域経済に関する情報を専門的に取材しています。
所属しているのは、全国紙の経済部や通信社、ローカル紙の経済・地域担当記者、中小企業向けメディアの記者などが中心です。
東商記者クラブには、主に以下のような中小企業・商工業・地域経済に関する情報が集まります。
- 中小企業の業況判断や経営環境に関するデータなどの景況調査の結果
- 補助金・助成金に関する案内
- 中小企業の新商品発表やスタートアップ
■日銀クラブ
日銀クラブは、日本銀行本店内に設置されており、金融政策、景気動向、マクロ経済に関する情報を専門的に取材しています。
日銀クラブは、日本の金融報道の最前線ともいえる非常に専門性の高い記者クラブであり、所属するのは全国紙の経済部・金融担当記者、テレビ局の経済記者、金融専門誌の記者が中心です。
なお、金融政策や証券市場に関する高い専門知識が求められるため、ベテランの記者が多い傾向があります。
日銀クラブには、主に以下のような金融政策や景気動向に関する情報が集まります。
- 政策金利(短期金利・長期金利)の変更など、金融政策に関する決定事項
- 成長率(GDP)の予測や物価動向など、経済・物価の見通し
- 金融システムの安定性に関する発表など、マーケット関連の情報
■都庁記者クラブ
都庁記者クラブは、東京都庁内に設置されており、東京都に関する情報を専門的に取材しています。
所属するのは、テレビ局、新聞社、通信社などの主要メディアの記者が中心ですが、ローカルメディアや、都政専門メディアの記者が参加している点も特徴です。
都庁記者クラブには、主に以下のような東京都の政策や施策に関連する情報が集まります。
- 東京都の予算案や政策に関する決定事項
- 東京都知事による施策の発表や方針表明
- 都内のインフラ整備や都市開発プロジェクトに関する情報
■農政クラブ
農政クラブは、主に農林水産省内に設置されており、農業・林業・水産業・食料政策に関する情報を専門的に取材しています。
所属するのは、全国紙や通信社の農政・経済担当記者、農業・食に特化した専門誌や業界紙の記者が中心です。
農政クラブには、主に以下のような農業や食の安全保障、地方経済に関する情報が集まります。
- 食料自給率、輸出入の状況、価格の推移など、農業経済に関する各種データ
- 農林水産省による農業政策や補助金制度に関する発表
- 畜産や漁業における制度改正、衛生管理、国際交渉に関連する情報
東京や大阪など都会の記者クラブと地方の記者クラブとの違い
東京・大阪といった都会の記者クラブと、地方の記者クラブの主な違いは、取材対象のスケールや情報の性質、発信力、所属記者の構成などです。
例えば、東京・大阪などの都会の記者クラブでは、国の政策や全国規模の経済・社会問題など、全国に影響を与える情報が主な対象となります。
一方、地方の記者クラブでは、地域行政や地元企業、地域イベント、災害など、地域密着型の情報が中心です。
また、都会と地方では、情報の発信力にも明確な差があります。
都会の記者クラブには、全国紙やキー局が多く所属しているため、発信された情報が瞬く間に全国へ拡散され、大きな影響力を持つ点が特徴です。
一方、地方の記者クラブは、主な読者が地域住民であることから、情報発信の範囲は地域内に限定される傾向があります。
さらに、都会と地方では、所属する記者の構成にも違いがあります。
都会の記者クラブは、全国紙や通信社、テレビ局の記者が多数所属しており、それぞれの分野に特化した記者が配置されるなど、分業体制が確立されている点が特徴です。
一方、地方の記者クラブは、地元紙やローカルテレビ局、全国紙の地方支局の記者などで構成されており、少人数で幅広いジャンルを担当するケースがあります。
このように、ひとくちに「記者クラブ」といっても、地域によって構成や役割などに違いがあり、入手できる情報の内容や傾向も多種多様です。
プレスリリース投げ込みのメリット

デジタル化が進んだ現在では、プレスリリースを投げ込みで配信する企業・団体は減少傾向にあります。
それでも今なお、このアナログな方法を取り入れているケースがあることをご存じでしょうか。
アナログには、デジタルにはない特有の魅力があるものです。
ここでは、プレスリリースの投げ込みをするメリットを解説します。
多くのメディアに一度に情報を届けられる
プレスリリースの投げ込みのメリットは、一度に多くのメディアに自社の情報を届けられることです。
特に複数の報道機関の記者が集まる記者クラブに投げ込みを行った場合、テレビや新聞、通信社などに同じタイミングで情報を届けることができます。
その結果、メールやWEB配信よりも、より多くの記者の目に留まる可能性が高いです。
記者と接点が作りやすくなる
プレスリリースを投げ込みで届ける場合、多くの記者と直接接点が作りやすくなるという、WEB配信やメールにはないメリットがあります。
記者と対面でやり取りができるため、熱意を伝えることができるほか、信頼関係の構築にもつながりやすくなります。
その結果、メディアへの露出につながる可能性も高まるでしょう。
低コストでできる
コストがかかるプレスリリース配信サービスや紙媒体とは異なり、投げ込みによるプレスリリースは、比較的コストが低くなります。
特に記者クラブに投げ込むことで、複数の報道機関の記者にまとめて情報が届くため、コストパフォーマンスはもちろん、タイムパフォーマンスが高いこともメリットです。
このように、限られたリソースで情報を届けられる点は、投げ込みならではの大きな利点と言えるでしょう。
プレスリリースの投げ込みのやり方
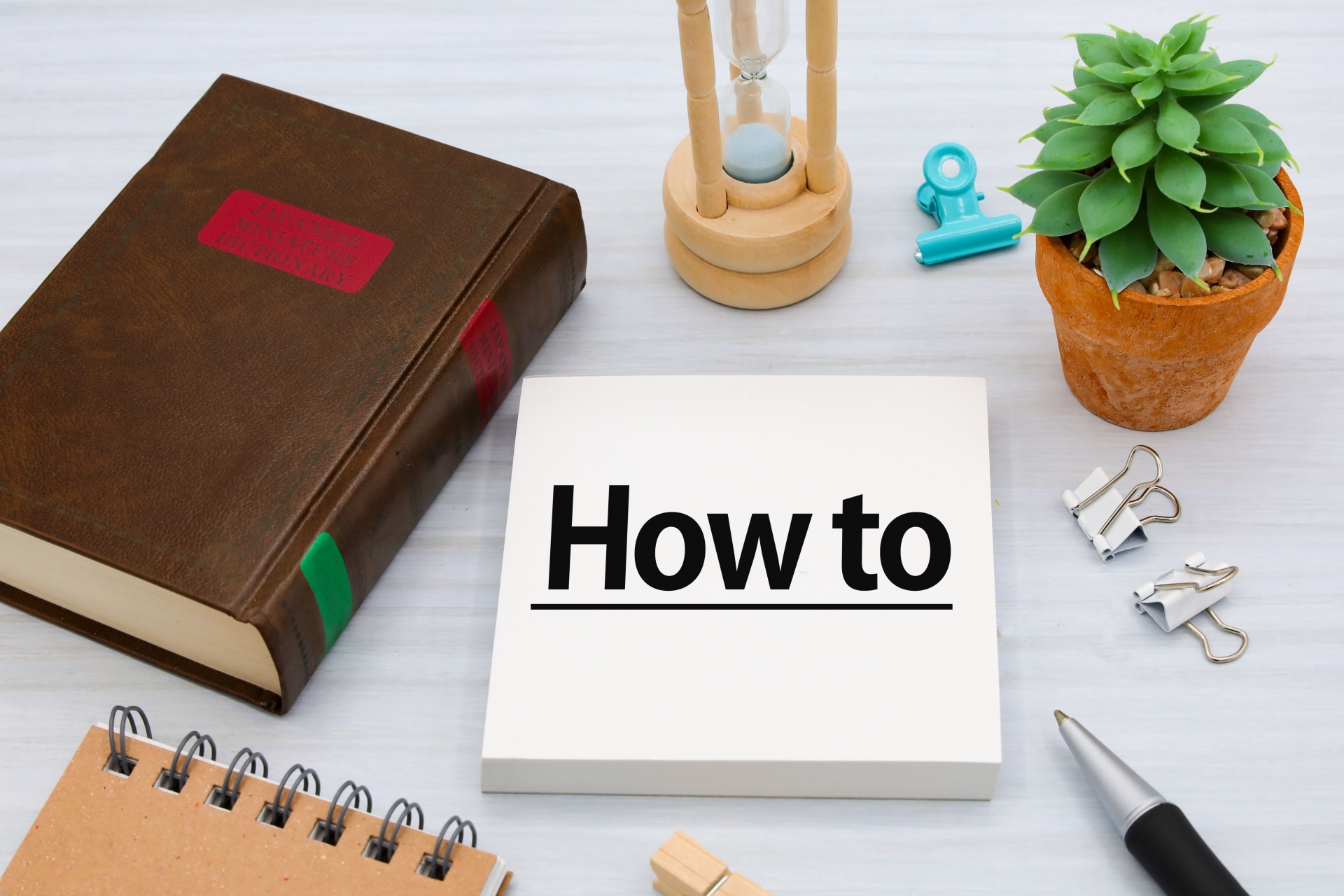
プレスリリースのメリットや特徴を知り、実際に試してみたいと考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、未経験の方は、投げ込みをする際に不安を感じることも少なくありません。
「そもそも、どのような手順で行えばいいのか?」と疑問を抱いている方も多いでしょう。
そこで、ここではプレスリリースの投げ込みのやり方を詳しく解説します。
1.投げ込みに適したプレスリリースの内容を決める
プレスリリースの投げ込みをする際は、報道価値が高く、記者クラブの分野に適合した内容を選ぶことが重要です。
例えば、最新のジェルネイルに関する発表であれば、文化記者クラブや民間放送記者クラブなど、ライフスタイルやトレンドを扱う記者クラブが適しています。
また、新技術の導入や特許取得など、技術的な要素を含む内容であれば、経済産業記者クラブが有効なケースもあるでしょう。
このように、プレスリリースを投げ込みで行う場合、まずはその内容に報道性があるかどうか、そしてどの記者クラブに適しているかを見極めることが大切です。
2.プレスリリースの投げ込み先を探す
プレスリリースの内容が確定したら、次はそれに適した投げ込み先を探します。
前項でも主な記者クラブをご紹介しましたが、その数は非常に多く、そこから最適な投げ込み先を見極めるのは簡単ではありません。
そんな時は、まず自社が発信したい内容と近いテーマで報道された過去の記事を調べてみましょう。
その記事の発信元を確認することで、どの記者クラブ経由で情報が報じられたのかを推測できる場合があります。
特に同業他社や近い業種の報道は、参考情報として非常に有効ですので、積極的にリサーチを行いましょう。
それでも適切な記者クラブが特定できない場合は、業界の広報担当者や経験者にヒアリングを行ったり、記者クラブに直接問い合わせたりすることが有効な手段です。
■コストとスケジュールを確認する
投げ込み先が定まったら、交通費や郵送代などのコストやスケジュールを事前に確認しておきましょう。
まずコストについてですが、投げ込みはデジタル配信とは異なり、紙のプレスリリースを印刷して持参することが多く、印刷代や資料作成費、交通費などの実費が発生します。
そのため、事前にこれらの経費が予算内に収まるかどうかを確認することが重要です。
次にスケジュールについてですが、記者クラブは受付時間が決まっていることが多いため、時間帯によっては対応してもらえない可能性があります。
せっかく訪問しても、受付外の時間であれば無駄足となってしまうケースもあるため、注意が必要です。
確実に情報を届けるためには、事前のスケジュール確認を徹底することを心がけましょう。
3.投げ込む記者クラブに連絡をする
プレスリリースの内容や投げ込み先が確定し、コスト・スケジュールの確認が済んだら、いよいよ記者クラブに連絡をします。
その際の連絡手段は、基本的に電話での事前確認が一般的です。
多くの記者クラブは無断訪問を避けるため、事前連絡を推奨していますが、これは訪問する側にとっても、記者の不在などで無駄足になるリスクを防げるというメリットがあります。
連絡の際には、投げ込みの可否や受付時間、注意点などを確認し、当日に失礼がないよう準備しましょう。
なお、記者クラブによっては、メールやFAXでの事前連絡や資料提出を求めるケースもあるため、あらかじめ連絡手段が適切かを確認し、状況に応じて柔軟に対応することが大切です。
また、事前連絡の際は忙しい時間を避け、用件は簡潔かつ明確に伝えるよう心がけましょう。
4.投げ込み方法と必要な部数を確認する
事前連絡の際には、投げ込み方法と必要な部数を忘れずに確認することが重要です。
記者クラブによって投げ込みのルールが異なる場合があるため、事前に確認しておくことで当日の対応がスムーズに進みます。
また、投げ込みでは、その場で必要な記者全員に行き渡るよう、適切な部数を持参することが大切です。
部数が不足すると情報が行き届かず、報道のチャンスを逃す可能性があります。
一方で、多すぎると無駄な印刷コストが発生するため、準備段階で必要な部数の確認が欠かせません。
■投げ込み時に添付する資料も用意する
投げ込み時には、プレスリリース本体に加えて、添付資料も用意しておきましょう。
記者は限られた時間の中で大量の情報を処理しているため、補足資料があると内容を短時間で把握しやすくなり、その結果として記事化につながる可能性が高まるからです。
なお、この添付資料の例には、新商品のイメージ画像、ユーザーへの調査結果のグラフ・図解などがあります。
5.プレスリリースを記者クラブに持参する
1〜4の準備が整ったら、プレスリリースと添付資料を記者クラブに持参します。
訪問前には、資料に誤字脱字や記載ミスがないか最終チェックし、事前に確認しておいた時間帯に訪問しましょう。
また、清潔感のある服装や身だしなみを心がけ、丁寧なあいさつやルール・マナーに配慮した対応を行うことも重要です。
投げ込み時の対応が良ければ、記者との良好な関係構築につながり、今後の広報活動においてプラスの効果が期待できます。
プレスリリースの投げ込みをするときの注意点

プレスリリースを記者クラブに投げ込む際は、適切な方法で行うことが大切です。
やり方を誤ると、今後の広報活動に悪影響が出たり、業界内での信頼や評判を損ねたりするリスクがあります。
そこで、ここからはプレスリリースの投げ込みをするときの注意点を解説するので、ぜひ参考にしてください。
適切な時間・タイミングで投げ込みをする
前項でも触れたように、プレスリリースの投げ込みをする際は、適切な時間帯やタイミングを選ぶことが非常に重要です。
記者クラブでは日々多くの情報が飛び交っているため、多忙な時間帯に持ち込まれたプレスリリースは、目を通されない可能性があります。
特に午前中や昼前後は、会見対応や締切などで記者が忙しい記者が忙しい時間帯です。
そのため、午後の落ち着いた時間帯に訪問するのが望ましいとされています。
また、記者クラブによっては、投げ込みを受け付ける時間帯が指定されている場合もあるため、訪問前には必ず確認しておきましょう。
記者クラブのルールを事前に確認する
プレスリリースを記者クラブに投げ込む際は、事前に各クラブのルールや運用方針を確認することが非常に重要です。
記者クラブには、それぞれ独自の運用ルールや方針があります。
これらを無視して投げ込みを行うと、受理されなかったり、記者に多大な迷惑をかけてしまうこともあるため、十分な注意が必要です。
なお、投げ込みの際に確認すべき代表的な事項として、受付時間や受け入れの可否、必要部数、提出資料の形式などが挙げられます。
■間違った方法でブラックリストに追加されてしまうことも
プレスリリースの投げ込みを行う際、事前確認を怠ったり、不適切な形式で提出したりすると、ブラックリストに追加される可能性があります。
記者クラブや各メディアは、報道や取材に関するルールを厳格に守っていることが多く、間違った手順を踏むことで信用を失うリスクがあるため、注意が必要です。
宣伝や広告目的の持ち込みはしない
プレスリリースの投げ込みは、あくまで報道資料として扱われることを前提に行われるものです。
そのため、宣伝や広告を目的とした持ち込みは原則NGとされています。
明らかに営利目的とみなされる内容を持ち込むと、記者に敬遠され、信頼を損なう可能性があるため注意が必要です。
投げ込みを行う際は、内容が宣伝色の強いものになっていないかを再確認し、話題性や報道価値がある情報かどうかを自問するようにしましょう。
情報量と発信するタイミングは揃える
プレスリリースの投げ込みを行う際は、情報量と発信のタイミングを揃えることが重要です。
情報量が不足したまま発信すると、記者から内容が薄いと判断されてしまう恐れがあります。
一方、どれだけ情報が充実していても、発信のタイミングが適切でないと情報の鮮度が落ち、他の話題に埋もれたり、報道価値が下がったりする可能性があるため注意しましょう。
投げ込みを効果的に行うには、情報の量や質、そしてタイミングを揃えることが不可欠です。
プレスリリースの内容に沿った記者クラブを選ぶ
前項でも解説したとおり、プレスリリースの投げ込みを行う際は、その内容に沿った記者クラブを選ぶことが非常に大切です。
記者クラブはそれぞれ、所属記者の専門分野や担当ジャンルが定められているため、関係のないクラブに提出しても、「自分の分野ではない」と判断され、スルーされてしまう可能性があります。
なお、内容に沿ったプレスリリースの探し方については、「プレスリリースの投げ込み先を探す」の項目をご覧ください。
同時に別のアプローチも行う
投げ込みを行う際は、同時に別のアプローチをとり、記者の目に留めてもらう工夫をすることが重要です。
これまでもお伝えしてきたとおり、記者クラブには、日々大量の情報が届いています。
そのため、単に投げ込むだけでは、他の情報に埋もれてしまい、記者の目に留まらない可能性がある点には注意は必要です。
特におすすめの対策としては、個別連絡(電話・メール)によるフォローアップが挙げられます。
記者に対して「この件ですが、もしご関心があれば取材いただけませんか?」と一言添えるだけでも、反応が得られる可能性があるでしょう。
また、投げ込みとは別に、SNSや自社サイトでの情報発信も効果的です。
公開情報として広く共有しておくことで、他の記者の目に留まる可能性が高まります。
まとめ

今回は、プレスリリースの投げ込みに関する情報をお届けしました。
プレスリリースの投げ込みは、多くのメディアに一斉に情報を届けられる、有効な広報手段のひとつです。
その効果を最大限に引き出すためには、記者クラブの特性をよく理解し、内容に適した場所とタイミングで行う必要があります。
また、投げ込みの際には、記者クラブごとのルールを事前に確認し、形式や提出方法に細心の注意を払うことも重要です。
単に「配る」のではなく、「どう届けるか」を意識し、個別連絡やSNSなどの別のアプローチを組み合わせることで、報道につながる可能性が大きく高まります。
これからプレスリリースの投げ込みを検討されている方は、しっかりと準備を整えたうえで、効果的に取り組んでいきましょう。





